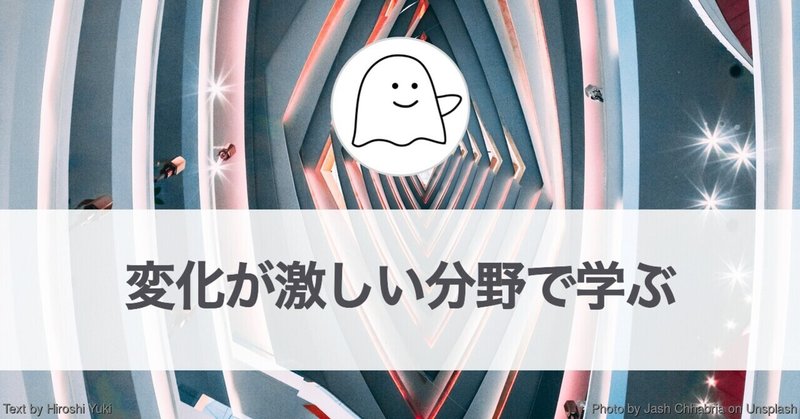
変化が激しい分野ですぐに古くなる知識をどう学ぶか(仕事の心がけ)
質問
コンピュータ関連の技術では、勉強した知識がすぐに古くなって役に立たなくなるものが多い印象があります。
結城さんは、コンピュータ関連のことで「必要だから勉強するけど、本音をいえば、すぐに古くなってしまうから勉強したくない」と思うことはありますか。
もしそう思うことがあるなら、その気持ちにどう折り合いをつけていますか。教えていただけるとうれしいです。
結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2018年2月27日 Vol.309 より
回答
ご質問ありがとうございます。
これは気持ちが非常によくわかる質問です。
変化が激しい分野で勉強しなければならないのは、なかなかつらいものがあります。
基本的に私は「できるだけ古くならない知識に関連した仕事をしよう」とは心がけています。「すぐに古くなる知識」を学ばなければならない状況のときには、「学び方を含めて学ぶ」ように心がけています。
以下のページにも書きましたが「時代に追いつくのが大変なのは自分だけではない」という視点も大事です。そこに飯のタネがある可能性があるためです。
情報不安について
ここから先は
1,158字
/
1画像
¥ 200
いただいたサポートは、本やコンピュータを買い、さまざまなWebサービスに触れ、結城が知見を深める費用として感謝しつつ使わせていただきます! アマゾンに書評を書いてくださるのも大きなサポートになりますので、よろしくお願いします。 https://amzn.to/2GRquOl

