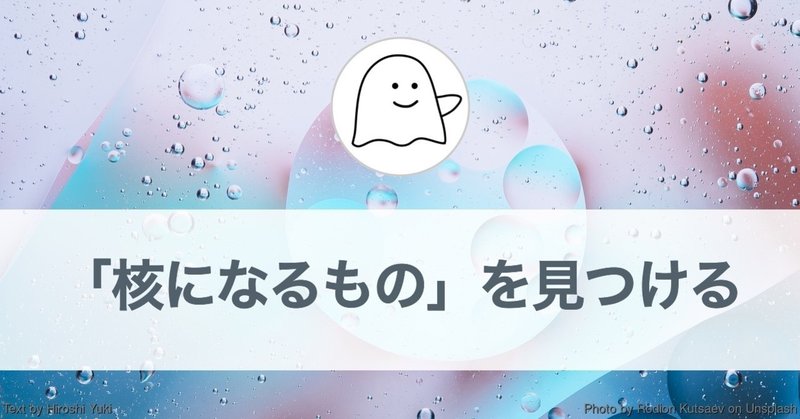
「核になるもの」を見つける(仕事の心がけ)
自分の活動で「核になるもの」を見つける話をしましょう。
結城は『数学ガール』をはじめとする本を書くのが仕事なので、自分の本に関する話をします。でも、きっと、あなたご自身の「核になるもの」を考えるきっかけになると思います。
結城浩の「コミュニケーションの心がけ」2017年4月25日 Vol.265 より
「伝えること」は核になる
「本を書く」とは、読者に何かを伝えることです。本にとって「核になるもの」は、読者に伝えるその「何か」のことです。
結城はその「何か」を、《読者に伝えるたったひとつのこと》と表現することがよくあります。その「たったひとつのこと」を見つけなければ、そしてうまく伝えることができなければ、本を書く意味の多くは失われてしまいます。
ここから先は
2,454字
/
2画像
¥ 200
いただいたサポートは、本やコンピュータを買い、さまざまなWebサービスに触れ、結城が知見を深める費用として感謝しつつ使わせていただきます! アマゾンに書評を書いてくださるのも大きなサポートになりますので、よろしくお願いします。 https://amzn.to/2GRquOl

