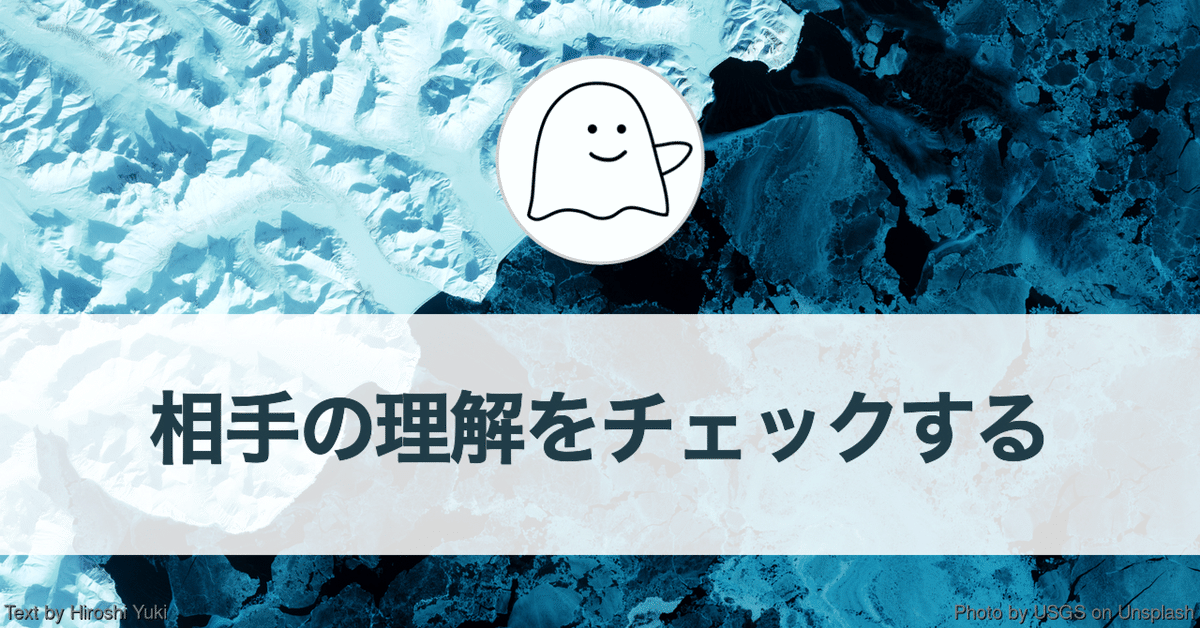
「ほんとうに相手は理解しているのか」をチェックしたいときに(コミュニケーションのヒント)
こんにちは、結城浩です。
今日は、「ほんとうに相手は理解しているのか」をチェックしたいときにどうするかというお話をします。
打ち合わせにおける対話の例
A「じゃ、そういう手順でお願いします。ここまでの話、わかりました?」
B「わかりました」
さあ、ここで問題です。
いま「わかりました」と言ったBさんは、ほんとうに「わかった」のでしょうか。
わかったかもしれないし、わかっていないかもしれませんよね。「わかりました」と言うことは誰でもできますが、実際にわかっているとは限りません。別にBさんが嘘をついているといいたいわけではなく、本人はわかったつもりになっているけれど、Aさんが求めるほどの理解に達していないかもしれないということです。
では、どうやってBさんが「わかっている」かどうかを確かめたらいいのでしょうか。
こんなふうに「念を押す」ように尋ねればいいでしょうか。
△「ほんとうに、わかりましたか?」
いえいえ、このような聞き方をしても、あまり意味はありません。「ほんとうに、わかりましたか?」と尋ねて「いえ、実は、よくわかっていません」と答える人は少ないでしょう。だからそのような「念を押す」だけの確認には、あまり意味はありません。
角度を変えて問う
相手の理解を確認したいのであれば、「角度を変えて問う」ほうがよいですね。
ここから先は
1,036字
/
1画像
¥ 200
期間限定!PayPayで支払うと抽選でお得
あなたからいただいたチップは、本やコンピュータを買い、多様なWebサービスに触れ、結城が知見を深める費用として感謝しつつ使わせていただきます! アマゾンに書評を書いてくださることも大きな支援になりますので、よろしくお願いします。 https://amzn.to/2GRquOl

